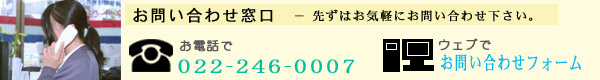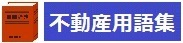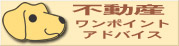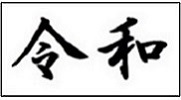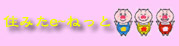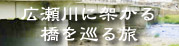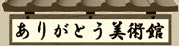2025年5月号 | レポート
<心に青春の歌を育む>
Ⅰ【 心に青春の歌を育む 】
1)孔子が晩年になって人生を振り返った言葉として論語(散文)が有名です。
(原文)
十五歳を「志学(しがく)」、三十歳を「而立(じりつ)」、四十歳を「不惑(ふわく)」、五十歳を「知命(ちめい)」、六十歳を「耳順(じじゅん)」、七十歳を「従心(じゅうしん)」と、いうようになった。
(書き下し文)
「子(し)曰く、
吾十有五にして学に志す。
三十にして立つ。
四十にして惑わず。
五十にして天命を知る。
六十にして耳順ふ。
七十にして心の欲する所に従って、矩(のり)を踰(こ)えず※1」
(訳:現代語訳)
「先生がいわれた。
わたしは十五歳で学問を志し、三十歳になると、独立した立場を得た。四十歳になると、迷うことがなくなり、五十歳のときに天命を理解する。六十歳になると、人のいうことを素直に聞けるようになって、七十歳になるとやっと自分の思うままに振舞っても人の道を外れるということはなくなった※1。」
(眠れなくなるほど面白い(山口謠司著(日本文芸社))より引用。)
2)けだし、「論語」は今から約2500年前に、中国で儒教を説いた漢の時代の孔子の言葉を記したものです。
たまたまネット上で「品があって憧れる!60代女優ランキング」の中で1位に選ばれた女優、俳優。人生のさまざまな出来事を乗り越えてきたためなのか、落ち着きがあり品性を感じさせる人も多い中でのランキングを見ました。
3位 宮崎美子
2位 薬師丸ひろ子
1位 ???(誰か?)
:
1位は「黒木 瞳」
黒木さんは、1981年に宝塚歌劇団に入団し、娘役トップスターとして活躍された。(タレントデータバンクより引用)
そんな黒木さんは、自分の生き方について感想を述べられています。
何歳だからこうあるべき、ということは意識していないと言います。
「四十にして惑わず、五十にして天命を知る」という前記の孔子の言葉を引用し、2023年時点で自分はまだ不惑の感覚だとコメント。そして、今の自分にできることを考えるべきだと語っていました。
(芸能ライター 田辺ユウキ の記事を引用。)
3)筆者も齢(よわい)75歳を過ぎ、今年76歳を迎えることとなります。年齢を重ねるということはどういう意味を持つのだろうか?孔子は73歳で死去するまで、書物を編纂し、秀でた弟子72人の他に3,000人の弟子を育てたと言われています。
一方、近代社会に於いては、齢(よわい)と共に弱まらない人がいて、「年」を重ねてさらに磨きがかかる能力とは何があるのだろうか?
「高齢化社会」のフロンティアとして世界をリードする等の研究する専門家だちが発見した朗報について以下に記してみたいと思います。
4)それは、年齢と共に衰えない能力があるという。
2019年8月5日、トニ・モリスンが亡くなったとき、世界は最も影響力のある文学的「声」のひとつを失った、と報じられた。
だが、モリスンは文学的「神童」ではなかった。
39歳で世に出した小説「青い眼が欲しい」、70歳で小説4冊、児童書4冊などを出した。
84歳で小説「神よ、あの子を守りたまえ」が出版された。
思うに、90歳代で作品を生み出している作家は沢山いる。例えばハーマン・ウォークは97歳で「法の与え主」(未邦訳)を出版している。
故に、年齢は「話す」「書く」そして「新しい語彙」を学習する能力を衰えさせるわけではないかも知れません。
自身の仕事に対する社会的使命やある重要な事での偉業(農林漁業などや趣味としての絵画、陶芸、音楽、手芸)を含む自律神経に良い創造的なものが脳に対し、ポジティブな刺激を与え、心のリラックスを促進することの作用の働きが影響している可能性があるのかも知れません。
孔子は73歳、荘子は83歳、医王の孫思邈(そん しばく)は141歳、明の時代の音楽家の連銭は150歳まで生きたとする記録が残っているという。
文化人の平均寿命は一般人の平均寿命(58.4歳)の約2倍も生きたことがわかります。
<まとめ>≪年齢を重ねることは社会で有益?≫
年齢を重ねることで課題を解決へと導くドアが沢山ある様に思える。今こそ日本国内での暴力の多発や世界各地でのきな臭い動きの解決に必要な思いとして、自分の考えを持つことは大変良いが、その目的の貫徹を急ぐあまり手段を選ばず、自分の考えと違う者へ暴力を行使して排除しようとする者が少なくない。このことが理解されない限り、民主主義社会が危うくなることに気が付かなければならない。
筆者は幸いにも驥尾(きび)に付して生かされて齢を重ねられている。感謝感謝でもあります。
≪今こそ高齢者が身を律してこれまでの経験を生かして、より良い社会の構築の為、啓蒙することが急務である。≫
<注釈>
※1 孔子の論語中、六十にして心の欲する所に従って、『矩(のり)を踰(こ)えず』を、仙台一中(現、仙台一高)の初代校長 大槻文彦先生※2は、同校の校歌にその散文の文言を引用されています。
旧仙台一中(現仙台一高)校歌 (大槻文彦 作詞、岩城 寛 作曲)
1.青葉の山の深緑
すがすがしきを心にて
身をし重んじつつましく
矩をば踰えずまもるべし
2.<省略>
※2 三省堂発行の「大辞林」によると、
「大槻文彦(先生)」1847~1928
国語学者。江戸生まれ。大槻磐渓の子。
文部省の命を受け国語辞書 言海、のちの大言海を著す。また国文法所「広日本文典」等を刊行。
旧仙台一中(現仙台一高)の初代校長は記されてありませんでしたのが残念であります。私生活では先生は北四番丁の官舎に住んでいて、毎晩寝酒に地元の「鳳山」(現在は廃業)を4合飲んでいたとする会報がある。
以上